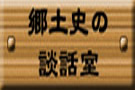 |
�@���쓹�i�����X�����ҕt�֓��j��H��
�@�@�i���y�j�ɂ�����k�b�@�V�S�j |
|

�Ή���̐����X���Ɠ��쓹�Ƃ̕���_ |
�@���ƊJ���̗��_�ɗN���]�ˎ��㖖���A���ď����ɂ��A�W�A�i�o�̏�̒��ŁA���ɊJ�`���}���܂��B
�@���ɊJ�`�i�_�ˊJ�`�j�ɍۂ��āA�O���l�����̋����n�ɉ����Đ����X�����ʂ��Ă���B ���l�̐��������i�O���l�E�������j�̂悤�ȏՓ˂��N���邩���m��Ȃ��̂ŁA�����X�����O���l�����n���I�ĎR����ʂ�A�Փ˂������Ȃ��ꏊ�ɕt�ւ����̂����쓹�ł��B
�@�����T�N�i1858�j�̓��ďC�D�ʏ����i���������j�ɂ��A�_�ސ�i���l�j�͈����U�N�i1859�j�ɁA���ɊJ�`�͕��v�Q�N11���i1863�j�̖��ł������B���������̌�̒����ɂ�靵�ΐ錾�❵�Θ_�̕����Ȃǂ����āA���̂R�����O�̓��N�W���ɁA���l�̐������ɂĎF���˂��s��������C�M���X�l���E�����������������u���A�F�p�푈�܂ň����N�������B����ŁA���ɊJ�`�͌c���R�N�i1868�j�ɉ������ꂽ�B
|
|
| �@���̌�A�J�`��~�̍����c�_�̕����Ȃǂ����čĂэ����B�c���Q�N�i1866�j���R�Ɩ̎����A�c���R�N�R���Ɏ��̏��R�c��͒���ƌ��A�J�`�̂ւ̌�������t�����B�P�Q������̊J�`�Ɍ����āA�O���l�����n�̖����đ����H���A�^�㏊�i�Ŋցj�̐����ȂǏ�����i�߂�Ȃ��ŁA���ɋ}���ꂽ�̂��A�u�����X���̕t�ցv�ł����B |
�u���@��@���v�@�H�@�}
 |
�@�����X�����ҕt�ւ��A�Ή��삩�番�A�[�J�A����R���A�����A���߁A����A���ˎR��ʂ�A�呠�J�ɂč������郋�[�g�Ƃ��āA����ɁA�Έ䑺�����̒J�����q�ƍr�c�������̊��슨�O�Y�������d�l���ǂ���11����19�C200���ŗ��D�������i�`���I�Ȃ��̂Ŏ��O���H���Ă����j�A�����H���͒J�����q���S�����B
�@�H���̕��S���������X�́A�ےÂƔd���̂Q���œp���S�A�����S�A���ΌS���̂S�W���i�����Z�g���ȂǂU���͎��O��������]�j�ŁA�������V�̂���{�́A�e�ˏ��̂����G�ɓ���������Ă���A�J�`���T���Ă̒����}��H���ł������B���ǁA�H���S�̂͂U�O���ȏ�������A�J�`�̂Q�T�Ԍ�ɂ͊����i�����R�ӏ��̏h�w�͖������j�������ƂɂȂ��Ă���B
�@�������A���H�͊������A�����������I�����Ă�����͖��{����x����ꂸ�A�J�����q�͑�ύ������B���{���疾���V���{�ւ̑̐��ϊv�̂Ȃ��A����Ǝx�����Έ䑺�̎���Ɏ��[�������A���B���Ɍ�p���Ƃ��Ėv�����D����Ă��܂��ߌ��ɑ����B�J�Ƃ͎��O�̎����ɂčH������̎x�����𑱂��������ł��B |
�@���̂悤�Ɍ�p���喇���g���A�ˊэH���ɂđ��J�̖��Ɋ����������ɂ��S��炸�A�������N�i1868�j�P���ɐ��{�x���̖��������O�˂͉��R���Đ����X����ʂ�A��C�������Ă����ꕔ�̕����������i�c�ɓ��j�E�R��������ĉ��ҕt�֓���������A�����n�O�̐_�ˎO�{�ŊO���l�ƏՓˁA�ꎞ���Ӓn����O���l�ɐ�̂����u�_�ˎ����v���N�������B�B��A�������N�������㑱���������ҕt�֓��𗘗p��������ƂȂ�A���̈ꕔ�͓c���ɖ߂��ꂽ��A�n���ł����p���邱�Ƃ����Ȃ��A���ɔp��B
�@�����������ɂȂ��ĘZ�b�R�S���t��J�݂�O���l�����̓o�R�O���[�v���n�C�L���O�������C�A���������X�����ҕt�֓��������������u���쓹�v�ƌĂB����ɂ��A�n�C�L���O�R�[�X�݂̂Ȃ炸�A��ʓI�ɍL���t�֓��S�̂��u���쓹�v�ƌ����悤�ɂȂ����B |
| �@���쓹�̃R�[�X�ɂ��ẮA�p���̌��쉻�A�����Q�ɂ�����A�ߑ㉻�ɔ����_�n���ǍH����c�n�����Ȃǂɂ�茳�̓y�n�`���ł�����A�H�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�����������������B�Õ����i�J�ƕ����Ȃǁj�ɂ��鏬���n���̉�����n��ł̕s�`���Ȃǂ����Đ��肷�邵���Ȃ�����������B�����ɁA�_�ˎs�����S�ƂȂ��ď��a50�N�i1975�j�ɔ������������쓹�����ψ���̌��ʂɂ��u���쓹�v�̃R�[�X�H���Ă݂����B |
| ���u���쓹�v�S�s���H���ɂ��āi�������A���a�T�Q�`�T�R�N�����j |
�@�@�@���H���}�i�g��Łj�́A���i�� �{�^�����N���b�N���ĉ������B �{�^�����N���b�N���ĉ������B |
| �H����� |
�J�ݎ��H����� |
���a�T�R�N�����̓��ؐ���} |
�E�@�v |
| �Ή���
�@�`�[�J |
�i�P�j�Ή����A���䑺�@�n�� |
|
�E���������l�����ɉ����Ėk��
�E�����Q���삩��Ή���E�݁i�����j��
�E�E�݂싴���l�܂� |
| �i�Q�j���쑺�A���H���@�n�� |
|
�E���싴���l���琼�֍��H�X�ǑO�� |
| �i�R�j�������@�n�� |
|
�E�����_�Ђ������A��������̂͒����i���͂Ȃ��j�ō�}�d�S�u��}�Z�b�w�v������ |
| �i�S�j�����@�n�� |
|
�E��}�d�S���z���āA�썑�_�Ђ֓��Ȃ�� |
|
| �[�J
�@�`����R�� |
�i�T�j�����O�P�Q�J������R |
|
�E�������w�Z����所����ʂ�A�͌��ɍ~���
�E�[�J�쉈���ɖk��A�[�J���Ɏ���
�E�����z���ĉ�����h���C�u�E�F�C������A�J�Ԃ̗���ցi�k���j
�E�����J���� |
|
�E�����J�Ί_�ՁA��Γn���Ȃ�
�E�z������k�サ�Ă������i�g�F���e�B�N���X�j�ƍ����A��J����
�E���J�r�i�X�ѐA�������j���琼�Z�b�h���C�u�E�F�C�� |
|
| ����R��
�@�`���� |
�i�U�j���������@�n���A
�@���������E������������n |
|
�E�X�ѐA�����k�傩��ܒ҂̊ւ̒�����
�E���Z�b�h���C�u�E�F�C�𐼂�
�E���������h���C�u�E�F�C���痣�ꖭ����L�n�X���ցi�������̓�j
�E�L�n�X����n��A���a��闖����ʂ� |
|
�E�D��Ղ𐼂֓��Ȃ�ɐ_�˓d�S��
�E�_�˓d�S���e��쉺�i���͕s���j�A�闖��ϓd�����ʂ� |
| |
�E�_�˓d�S�i�O�c���j���z���k�������
�E������O��闖�䐼���w�Ő��H�쑤��
�E�闖������ʂ�A���a��c�n�� |
|
| ����
�@�`���� |
�i�V�j���ߑ��@�n��
�i�W�j���K�r���E���K�r���E
�@�r�c�E���c���S�J��
�@�����R
�i�X�j���쑺�@�n�� |
|
�E���a�䏬�w�Z�����J�z���ցi�����̖ʉe�S���Ȃ��j
�E���߁`����Ԃ̃n�C�L���O�R�[�X�ցA���쑺���ʂ֓쉺 |
|
| ����
�@�`���� |
�i�X�j���쑺�@�n�� |
|
�E��ΐ_�Љ���_�ˎO�ؐ���
�E����k����������𐼂֕z�{���ցi�ےÔd�����B�̋��E�W�����������y��̂݁j |
|
| ����
�@�`���ˎR |
�i�P�O�j�z�{�����@�n��
�i�P�P�j�������@�n�� |
|
�E�Ҋ��J�𐼂ցA�����ցi�c�n�������Ӂj |
�i�P�Q�j��O���@�n��
�i�P�R�j�������@�n��
�i�P�S�j���⑺�@�n�� |
|
�E�n�C�L���O���́u���z�Ɨ̓��v���s��
�E���̐}���ł͊w���s�s�J���œ��s��
�E�������������˗��_�Ў�Ԃ���E�֒�����ʂ� |
|
| ���ˎR
�` �呠�J |
�i�P�T�j���R���A�呠�J��
�@�n�� |
|
�E���⏬�w�Z�O���琼�_�ˊw�@��w��
�E���R�����疾�Ζ�����M�����ʂ�
�E�c�n������E�݁i�����j�֎߂ɍ~���i���̕ӂ̓��͕s���j
�E�쉈����쉺�������X���� |
|
���u���쓹�v�S�s���H���̒n�}�i���a�T�R�N�����j |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ���S�s���H���ɂ��ẮA�w���쓹�E�����X�����ҕt�֓��j�x�������i���a�T�R�N�A�_�ˎs���쓹�����ψ���j�ɂ��B |
| ���u���쓹�v��H�� |
�@�u���쓹�v�̘H���ɂ��ẮA�J�݂��ꂽ�������N�i�P�W�U�W�j�����P�O�O�N���o�čs��ꂽ�_�ˎs�̒�������X�ɖ�T�O�N���o�߂��A���̊Ԃ̎s�X�n�����A�_���J���A���H�����A���Q���ɂ�����Ȃǂ����āA���a�T�R�N�����̗l�q������傫���ϖe���Ă��Ă���B
�@���݂̏ɂ��ẮA���ۂ̓��������{���邱�Ƃɂ���Ĕ������邱�Ƃ����҂����B�@���쓹�S�s���i�R�S.�T�����j�̌���́A���L�̍s���ɂ��������o�Č���i�f�ځj�������B�݂Ȃ�����h���h�����킵�Ă݂ĉ������B
�i�Q�O�Q�O�N�S���j |
|
�������ق̃z�[���y�[�W���Œ��Ă���e�L�X�g�A���j���A�ʐ^�A�O���t�B�b�N�X�A�f�[�^���̖��f�g�p���ւ��܂��B |
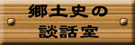 ���N���b�N���ĉ������B
���N���b�N���ĉ������B
�u���y�j�̒k�b���v���j���[�@�֖߂�܂��B |
 ���N���b�N���ĉ������B
���N���b�N���ĉ������B
�u�_�ˁE���ɂ̋��y�j�v���������ف^�n��n���E�c�[���Y���������v�̃g�b�v�E���j���[�֖߂�܂��B |
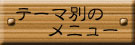
���N���b�N���ĉ������B
�u�e�[�}�i�ۑ�j�ʃ��j���[�v�@�֖߂�܂��B |
|

