

|
|||||||||
 日本で最初に古代の駅家(駅館院)の実態を発掘解明した「布勢駅跡(小犬丸遺跡)」 |
|||||||||
|
|||||||||
| 駅路の重要性から、道幅や整備される駅馬の数などの規模も最大でした。古代の道、特に山陽道とはどんな駅路だったのでしょうか。 飛鳥時代に設置された駅(前期駅家)は、奈良時代に瓦葺きで礎石をもつ建物に建て替えられました。これ以後を後期駅家と区別しています。 古文書『日本後紀』の大同元年(806年)に記された山陽道の駅家の修理・整備については、「前制」のとおり修理し、新整備には「定様」に従うように、と記されています。すなわち、山陽道の駅家には基本的な仕様(整備マニュアル)が存在していたようです。 特に兵庫県内、播磨国の駅家には次のような仕様が想定されます。 ①全ての官道は「30里(約16km)ごとに1駅」と養老令(757年施行)にあるが、播磨国ではその半分の15里ごとに駅が設けられました。 ②眺望が開けた立地、高台や峠下や平地がえらばれている。 ③周辺地域には位置は様々だが、同時期に寺院が建立されている。 ④駅家の中心建物「駅館院」は、山陽道に近接して正方位(後期。前期は道沿い)で駅家を配置。面積は約6,400m2(後期。前期は約700m2、正方形)。建て替えには若干近隣に移設もある。内部の建物配置はコの字形・中庭の古代の役所と共通する。駅館院の建物は、「瓦葺粉壁」(瓦屋根で朱塗りの柱、白壁造り)で整備。正門はいわゆる礎石や石の唐居敷のある豪華な「八脚門」で、南向きが基本だが道の方向に設置されたものもある。瓦には、役所と同類の「播磨国府系瓦」が使用されていた。 そもそも古代の道は、 基本的に直線道路になるように路線を決定している。集落を経由する日常利便性を考慮せず、平坦路で少々のことなら切通しや埋め立てして路線を確保した。また、一定の幅広(12m前後)の道路幅員を確保していた。後に(9世紀~)5,6mに半減(改変)させていた。駅路の両側に側溝や並木が植栽されていた模様。 駅家の周辺には、駅家関連の機能を果たす施設として、厩舎、牧場、厨房、専属の倉庫、遠くを眺望する塔の駅楼、駅管理事務所的建物が整備されていたと考えられますが、それら関連施設の解明についてはなかなか発掘調査は難しいところです。 |
|||||||||
| 古代の道「山陽道」の駅路と駅家 古代の道「山陽道」は、都と大宰府を結ぶ最大の幹線道でした。五畿七道の中でも「大道」としての格付けで、40里(約16km)ごとの豪勢な瓦葺粉壁の駅家、駅馬も20匹を常備していました。『延喜式』によると、京都を出た山陽道は、「山埼駅」(京都市)、「草野駅」(箕面市)を経由し下河原(伊丹市)あたりから兵庫県内に入ります。 下図の路線概略と駅家については、『延喜式』には「邑美駅」と「佐突駅」の記載がないので、当時は廃止されたものと思われます。駅路は、平野部は直線的に、高い丘は迂回しながらも極力短距離を、また峠などは難路の程度和らげながら低地を地形に併せて通っていたようです。 |
|||||||||
 |
|||||||||
| 少し詳細な図面に基づき、駅路の重要な通過地点および駅家跡などを見てみましょう。駅路については、まだ確定された部分は少なく、気象条件に左右される駅路もあって、迂回路を含めて種々学説があります。また、駅家の位置も発掘等で確認された「邑美駅」「賀古駅」「大市(邑智)駅」「布勢駅」「高田駅」「野磨駅」を除いて諸説の候補地がありますが、とりあえず、私なりの一考察を加えてみました。 それでは、古代山陽道の駅路を辿ってみましょう。 | |||||||||
| (1)大阪府の草野駅(大阪府)西方の県境付近~「葦屋駅」 | |||||||||
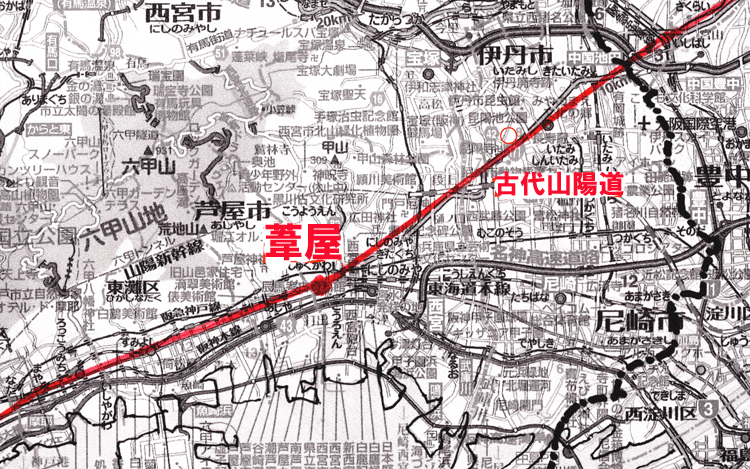 |
|||||||||
|
|||||||||
| 【未確定の仮称「昆陽駅」存在の可能性について】 昆陽寺は、古代において南側を通る山陽道と、東側を通る難波宮~有馬の連絡道(推定)との交差する地割りにあり、ここに廃止された駅家(仮称「昆陽駅」が存在した可能性が指摘されています。昆陽寺境内遺跡において、9世紀代の土坑から須恵器や土師器が発掘されています。 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| (2)「葦屋駅」~「須磨駅」~「明石駅」 | |||||||||
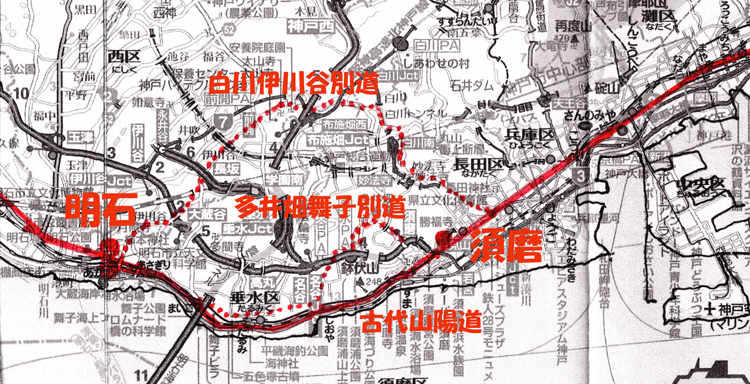 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【「須磨駅家」から「明石駅家」に至るまで、4つ考えられる駅路ルートについて】 「須磨駅」と想定される太田町遺跡から「明石駅家」に至る駅路ルートについては4案ある。上記の須磨駅から明石駅への駅路は本道とされているルートです。 この本道のほかに、別ルートが考えられています。下記のうち、(1)が本道とされるもの。ほかに(2)~(4)の別ルート(別道)3案が迂回路として考えられています。 (1)「本道(海岸路)」=前田公園周辺「須磨駅家」~境川~塩屋~滝の茶屋~舞子公園~朝霧~「明石駅家」 (2)「白川伊川谷路」=「須磨駅家」~板宿~白川峠~大山寺~伊川谷~長坂~「明石駅家」 (3)「多井畑塩屋路」=「須磨駅家」~多井畑峠~多井畑神社~塩屋~滝の茶屋~舞子公園~朝霧~「明石駅家」 (4)「多井畑舞子路」=「須磨駅家」~多井畑峠~多井畑神社~塩屋西~五色塚古墳~舞子公園~朝霧~「明石駅家」 この4つの駅路ルートのうち、気象条件によって通行の難易度が変わってくる。 |
|||||||||
| (1)本道(海岸路) 「本道(海岸路)」は最短距離であり、大雨や大風が無い日は利用されていたであろう。よって本道とみなされている。しかし、暴風雨にでもなろうなら、内陸の別道(迂回路)を通ったであろう。 |
|||||||||
|
|||||||||
| (2)白川伊川谷路 「白川伊川谷路」に入るには、太田町遺跡「須磨駅家」からがそう遠くなく、駅家手前の蓮池付近から北上し、妙法寺川(白川)と伊川谷を川沿いの比較的低地を進むが、かなり遠回り・長距離であることは否めない。 迂回路の候補として有力と言われている。しかし、上の地図で示すとおり、太田町遺跡だったとしても「須磨駅家」から東に戻って板宿から妙法寺川(白川)をさかのぼり、白川峠から伊川伝いに「明石駅家」を目指すには最遠距離の行程となります。 最近の現地踏査で、伊川の中流付近の長坂台地を南北に通じる古代の道の痕跡が確認されていますが、この白川峠を経由する伊川谷ルートが山陽道の本道ではなく、荒天時等の迂回路であった可能性は高いと思われます。 |
|||||||||
|
|||||||||
| (3)多井畑塩屋路 「多井畑塩屋路」については、須磨から塩屋にかけての断崖海岸路を避けることができるが、塩屋から海岸路を採ると、滝の茶屋の断崖・滝・狭い海岸があって、同様の難儀が降りかかり、迂回するメリットが半減する。 「須磨駅家」から悪天候時に内陸の迂回路に回る場合に、須磨鉢伏山の断崖波打ち際を避ければよいから多井畑神社から塩屋河谷を川沿いに塩屋に降りてきて、それから海岸路を行くことになる。しかし、塩屋から海岸路にもどれば、滝の茶屋付近の断崖を流れ落ちる多数の滝の影響を狭い波打ち際の道でさけるのは困難と思われます。 よって、塩屋から海岸路を明石駅へ向かうのは、多井畑へ迂回した利点がなくなるので、可能性は低い、と思われます。 |
|||||||||
|
|||||||||
| (4)多井畑舞子路(迂回路最適コース) 内陸の多井畑神社へは、奈良時代末期に畿内最西端に祀られた厄除け神社で、言わば常用の路。ここから「明石駅家」へは、ほぼ直線的に西方に進むのが最短である。 悪天候時の迂回には、塩屋の海岸に降りて本道に合流せずに、塩屋内陸から断崖上の台地を五色塚古墳の北側道路(史料に存在)を通り、途中の高丸(垂水区)地区などの複数の尾根を横断して海岸の幅広く松林が広がる舞子にて本道(海岸路)と合流する「多井畑舞子路」なら、崖下の海岸路を避けて、なおかつ距離的なロスが無いことから選択されるべき迂回路のコースと思われます。 それで、この(4)のルートが最近注目されています。 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| (3)「明石駅」~「邑美駅」~「賀古駅」~「佐突駅」 | |||||||||
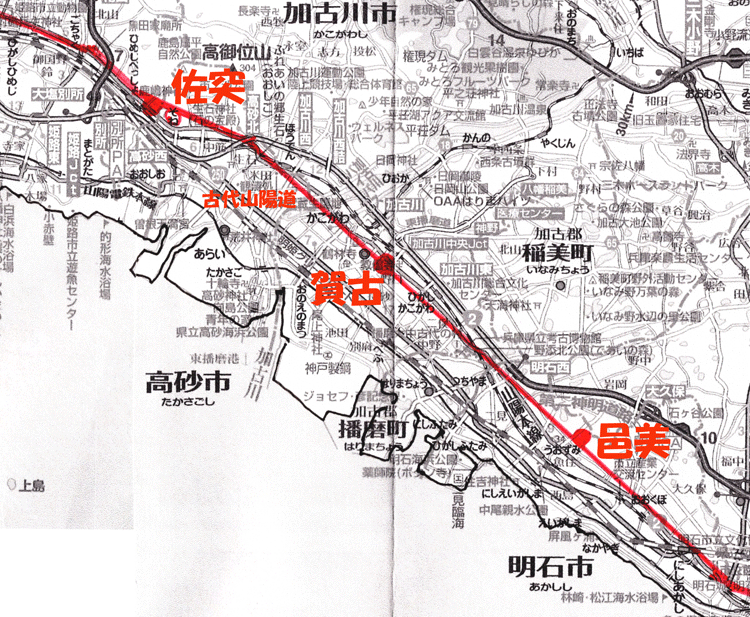 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| (4)「佐突駅」~「草上駅」~「大市駅」~「布勢駅」 | |||||||||
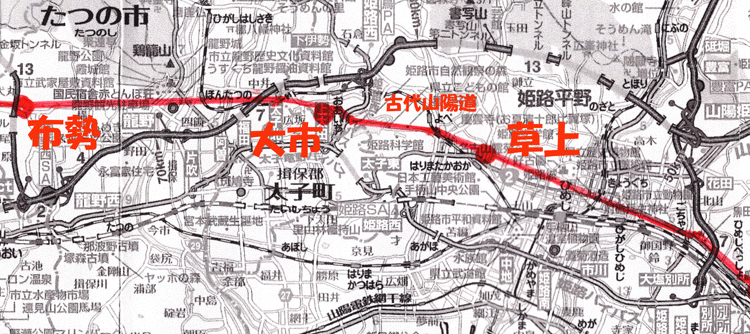 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| (5)「布勢駅」~「高田駅」~「野麿駅」~県境から岡山県側(坂長駅)へ | |||||||||
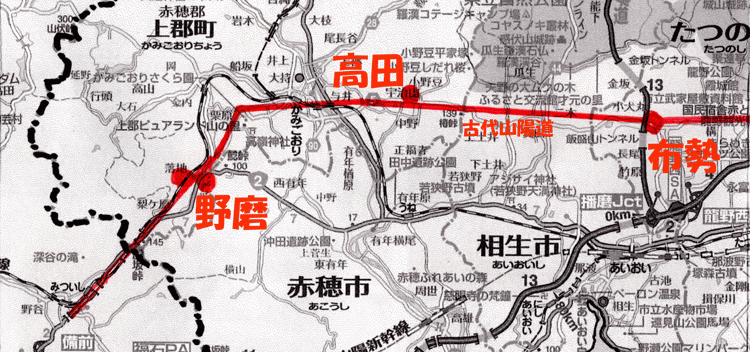 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 山陽道の駅路や駅家については、全国的にみて比較的に比定が進んでいるが、まだまだ分からない多くの地点が残されています。今後も、更なる発掘調査、研究が望まれます。(2025年10月) | |||||||||
| ※参考にした資料: ・『兵庫県古代官道関連遺跡調査報告書1~5』兵庫県立考古博物館、 ・『歴史の道調査報告書全集9“近畿地方の歴史の道9”兵庫1』兵庫県教育委員会(海路書院)、 ・『歴史の道調査報告書全集10“近畿地方の歴史の道10”兵庫2』兵庫県教育委員会(海路書院)、 ・『山陽道駅家跡~西日本の古代社会を支えた道と駅~』岸本道昭著(同成社)、 ・『完全踏査・続古代の道(山陰道・山陽道・南海道・西海道)』武部健一著(吉川弘文館)、 ・『古代官道・山陽道と駅家~律令国家を支えた道と駅~』兵庫県立考古博物館、 ・『明石の古道と駅・宿~発掘された明石の歴史展~』明石市ほか、 ・『駅家発掘!~播磨から見えた古代日本の交通史~』兵庫県立考古博物館、 ・『ひょうごの遺跡』兵庫県立考古博物館、 ・『古代道路の謎~奈良時代の巨大国家プロジェクト~』近江俊秀著(祥伝社)、 ・『日本の古代道路を探す~律令国家のアウトバーン~』中村太一著(平凡社) など |
|||||||||
| ※下の「写真」をクリックして下さい。
|
|||||||||
当研究館のホームページ内で提供しているテキスト、資史料、写真、グラフィックス、データ等の無断使用を禁じます。 |
|||||||||